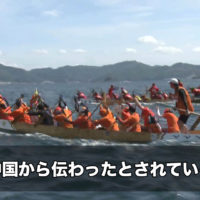●日本で開催された海洋の国際会議に世界の専門家が集結
世界最大級の海洋国際会議「ワールド・オーシャン・サミット」が、初めて日本で開催されました。2025年3月12日から13日にかけて行われたこのイベントは、イギリスの有力メディアThe Economist Groupの「エコノミスト・インパクト」と、長年にわたり国内外で海の課題解決に取り組んできた「日本財団」が共催し、各国の首脳や国際機関のリーダー、専門家たちを迎えました。
●14歳の鋭い質問に海外の専門家も感心
海洋問題の最前線などについて議論を交わすこのサミットに、日本の中学生も参加。それが、前編で紹介した石野立翔さん、そして、鈴木瑛梨花さんです。14歳の鈴木さんは、幼い頃から海洋プラスチック問題や海の生物多様性に深い関心を持ち、それらをテーマにした自由研究などで数々の入賞実績を持っています。また、オーストラリアやアメリカで海に関する国際的な課題研究を実施していたこともあって英語が堪能。今回のサミットでは、その持ち前の知識と語学力を活かして、各分野の専門家などと積極的に会話し、学びを深めている様子でした。例えば、衛星画像から海中のブルーカーボンなどをマッピングする技術を提供している「TCarta」のブースでは、「地球上のどのあたりの場所が地図化するのに難しいですか?」と質問。すると、「北極はやはり難しい。氷があるし、融解後の濁りや高波もあるので。だから、良い画像を撮るのは確かに難しいが、できないかといえばもちろんできる」と教えてもらいました。
●化学物質による海洋汚染と未来へのアクションを10代が直撃
また、「海洋汚染ゼロへの長い道のり」という海の化学汚染について議論するパネルディスカッションにも興味津々。海洋プラスチック問題について研究していたように、海洋環境汚染の問題は鈴木さんがずっと追いかけてきたテーマのひとつです。登壇した国際連合環境計画(UNEP)の生態系部門ディレクターであるスーザン・ガードナーさんは「30年前に採択された“陸上活動からの海洋環境の保護に関する世界行動計画(GPA)は、とても重要な成果があったと思う。水銀や残留性有機汚染物質(POPs)への取り組みの必要性の認識、そして、プラスチック問題もこの頃の取り組みが出発点になっている」と話しました。また、日本財団の常務理事・海野光行さんは「日本財団は2050年までに有害な海洋汚染を無くすことを目指して、2024年に作成したロードマップを推進していきたい」と発表。こうした目に見えない波となって海を汚す化学物質についての議論は、環境問題に強い関心を持つ鈴木さんにとって特に響いたようです。そこで、登壇者のひとりだった海野さんに「2050年まで時間があまりない中で、効果のあるアクションやムーブメントをどのようにつくっていくかという話が(ディスカッションの中で)たくさんありました。今はまだ働いていない私のような学生にもできることはあると思いますか?」と、その思いを伝えてみました。すると、「たくさんの情報をまずは仕入れて欲しい。それがインプットされたら今度はアウトプットすることを考えて、同じ世代の仲間と議論をしてもらえたらいいと思う。鈴木さんの場合は語学が堪能なので、共通の言語でいろんなディスカッションができる。インプットしたものをアウトプットする相手を探して、どんどん議論を深めていって欲しい」と海野さんから助言と後押しをしてもらいました。
●拍手喝采!10代の学生にできる海洋酸性化の解決策を質問
ワールド・オーシャン・サミットは、2日間で60を超えるセッションが開かれます。鈴木さんが次に参加したのは、「海洋酸性化と生物多様性の喪失: 知識を行動に変える」というテーマのパネルディスカッション。登壇したプリマス海洋研究所科学部長 兼 副最高経営責任者のスティーブ・ウィディコムさんは「海洋酸性化は我々が日々行っている海洋環境モニタリングの中でも重要なこと」と話し、また、東京大学 大気海洋研究所の教授・藤井賢彦さんは「海洋酸性化の原因は2つある。ひとつは人間活動に伴うもので我々が排出する二酸化炭素が原因。もうひとつは(陸から影響を受ける)沿岸酸性化と言われるもの」と説明。貝類や甲殻類に著しい影響があるという海の酸性化については、国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が警告を発していて、日本では日本財団が2020年から定点観測を進めています。そんな現象について議論が交わされたこのセッションの質疑応答で、真っ先に手を挙げたのが鈴木さんでした。「私は14歳の学生です。もし海の酸性化を止めることが私たち学生の手に負えるものではないとしたら、10代の学生にはどんなことができるでしょうか? 個々人でも学校といった共同体単位やオンラインでのつながりも含めて聞かせて欲しいです」と質問したところ、その堂々とした姿に会場から自然と拍手が起こりました。そして、スティーブさんは「“海洋酸性化”という言葉を広めてください。あなたの言葉を使うのです」とアドバイス。また、OAアライアンスの事務局長ジェシー・ターナーさんからは「まずは、この問題について関心を持ってくれたことにありがとうと言わせて欲しい。学校の中でも仲間同士でもこういった国際会議の場であっても、あなたの声が届けられるというのは本当に素晴らしいこと。ありがとう」と応えてくれました。鈴木さんは今回のサミットに参加してみて「いろんな人に話しました。新しいものをつくっている人、いろんな経験を持つ人たちもいました。私が子どもの頃に憧れていた探検家もいて、すごい楽しかったです。そして、(海洋問題に対して)世界は何をしているのか、世界の政治はどうやって絡んでくるのかも学びました」と振り返っています。
●世界に届け!若き探究者の声と海への情熱
世界最大級の国際会議という場で、特別な体験をした2人のティーンエージャー。彼らは複雑化する海の課題にどう向き合うのでしょうか。若者たちの知恵と勇気に期待しましょう。