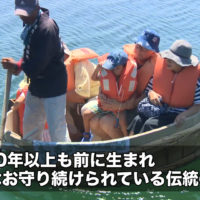●灯台は今、海の安全から地域の観光資源へ──進化する灯台の役割と利活用の広がり
11月1日から始まる「海と灯台ウィーク」に先駆けて、都内で「海と灯台サミット シンポジウム」が、2025年10月21日に開催されました。
イベント冒頭では、日本財団の笹川陽平名誉会長が映像を通じて「江戸時代の終盤まで日本の海は『漆黒の海』で光がなかった。明治の最初に初めて近代的な灯台がつくられて海の状況が一変した」と紹介したように、灯台は海上交通の安全を守る道しるべとして活躍していました。しかし今では、その役割を超えて、全国各地でさまざまな利活用が進んでいます。今回のシンポジウムは、2020年からそうした取り組みを推進したり、灯台を多角的に研究したりしている日本財団「海と灯台プロジェクト」が開催しました。
●伊沢拓司氏らが語る「灯台×旅」の新体験──有識者が示す次世代の灯台ツーリズム
今年は“旅”を入り口に、クイズプレーヤーの伊沢拓司さんをはじめ、さまざまな有識者が新たな灯台体験について語り合いました。まずは、伊沢さんと日本財団の海野光行常務理事が登壇。海野常務理事から「灯台が東京ディズニーランドに勝っているところを3つ挙げてください」といったように、伊沢さんが得意なクイズ形式で問いを投げかけ、灯台の魅力を深掘りしていきました。その後は、さまざまなジャンルの有識者が登壇し、「灯台×旅」を切り口に体験を語ったり、提案をしたりしました。動画クリエイターでバイカーのせんちゃんは「夕日×バイク×灯台だとかなり映える写真になる。そういう撮影スポットを提示してくれると、みんな自然にシェアしやすいと思う」と話し、一般社団法人グリーンスローモビリティ協議会の三重野真代理事長は「(灯台は)やっと着いたという達成感がすごく良い。その達成感の証を持って帰りたいので、“灯台カード”をつくってコレクション的に集められると面白い」と提案しました。また、癒し・歴史・食の観点から新たな魅力を探るパートでは、実際に灯台で行われている取り組みなどを紹介。その中で、気象予報士で防災士の久保井朝美さんは、歴史やお城マニアの視点から灯台の楽しみ方を提案。「玄界灘に面した佐賀県の唐津城。ここから北西へ行くとあるのが波戸岬(はどみさき)灯台。玄界灘に面していて航海が難しいけれども美味しい海の幸がある。どこにあるのだろう、なぜここにあるのだろうということを探っていくと、歴史がそこから浮かび上がってきたり、物語がいろいろ見えてくると思う」
●「海と灯台ウィーク」を前に展望!道の駅のように「何度も訪れたくなる灯台へ」
シンポジウムを終えて海野常務理事は「今回は旅と灯台を掛け合わせるような企画を行ってみた。1度行ったきりではなくて、2回3回と行ってもらうようにするためには、何が必要かを考えないといけない。ひとつ参考になる事例は道の駅だと思う。灯台においてどういうことができるのかをもう一度考えて、施策の中に入れ込んでいきたい」と今後の展望を語りました。
11月1日からの「海と灯台ウィーク」では、全国の灯台でさまざまなイベントが行われます。この機会に灯台への旅を考えてみてはいかがでしょうか。