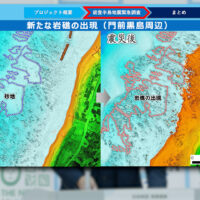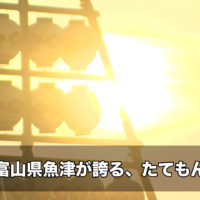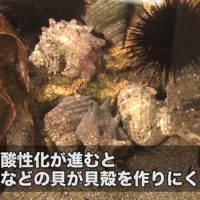カキの生産量で全国3位の岡山県。中でも瀬戸内市邑久町は県内有数の産地です。しかし、近年、増加したクロダイによって養殖のカキが食べられる「食害」が多発しています。邑久町漁協の松本正樹組合長は「年間で言うと、邑久町漁協だけでも1億円ぐらいのカキ養殖の食害が起こっている。生産者も色々な工夫をしているが、やはり増えたクロダイには勝てない」と嘆いています。漁業者にとってはたいそう困った魚・クロダイなのですが、実は食べてみると、とてもおいしいのだそう。そこで、このクロダイを使ったご当地弁当の開発が進められることに。生産者と消費者が共に喜ぶ、そんな一石二鳥の仕組みとなることが期待されています。料理研究家の喜多マリコさんがつくった試作品を食べてみた松本組合長は「おいしい」と絶賛。また、岡山県漁連の上柏恒一第二業務部長は「このお弁当をおいしく食べてもらって、どんどん生態系も普通に戻していって、消費者の認知も上げていきたい」と展望を語っています。
一方、北海道の根室では、ヒトデを使った驚きの取り組みが。ヒトデはホタテを食べてしまうため、地元の漁師たちにとっては頭の痛い存在です。そこで、根室の水産加工会社「吉田水産」がつくったのが、ヒトデを使った害獣忌避剤「強臭力(きょうしゅうりき)」です。漁業関係者から譲り受けたヒトデを、独自の方法で加工し、溶液に漬け込んで発酵させます。すると、強烈なにおいを放つ液体に。吉田水産 バイオ事業部の辻宰課長によると「検査機関にお願いして(においの)数値を測ってもらったが、においが強すぎて数値計測不可能となった」と話すほど。また、鹿を育てる牧場で実験も実施。白いエサ箱にだけ「強臭力」を入れると、近づいてきた鹿が飛びあがって逃げるほどの効力でした。道内のエゾシカによる交通事故は、2023年だけで5000件以上も発生。そこで、現在は大手電機メーカーと協力して、動物が来たらセンサーで反応して噴射する「自動噴霧装置」も開発中です。進化を続けるヒトデの利活用に今後も注目です。
そして、進化を続けている技術といえば「AI」。香川県の香川高等専門学校 宇宙開発研究部では、そんなAIを使って、漁業を支援しようと取り組んでいます。本科4年の齊藤壮志さんは「直島に行った際に、漁師さんから人材不足で困っている、魚が赤潮で死んでしまうと聞きました。そこで、僕たちにできることは何なのかと考えてこのシステムを開発しました」と話すものが「Seaサポ」です。これはAIを活用して赤潮の発生や移動の予測を行い、養殖の生産者などに通知する漁業支援アプリ。これまで手動のセンサーで測っていたものを自動化し、過去のデータをAIにディープラーニングさせることで、ほぼ100%に近い精度で予測できるようになったそうです。このシステムは、事業アイデアとビジネスプランを競う全国大会で、4億円もの企業評価額を得て、全国2位に輝きました。齊藤さんは「僕たちはこのプロジェクトを通して、もっと日本や世界で魚が食べられるようになって欲しいという思いがあり、もっと漁業が盛り上がればと思っています」と語っています。
素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトinガッチャンコ北海道」 「海と日本プロジェクトin岡山」 「海と日本プロジェクトinかがわ」
協力:北海道放送 山陽放送 西日本放送