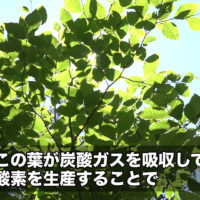スシロー東静岡店にて「熱源熱中授業」が3月31日に行われました。このイベントは、日本財団「海と日本プロジェクト」と回転寿司最大手のスシローがタッグを組み、全国各地で実施。毎回スシローのお店を教室として、地域の海を知りつくした「熱源先生」とスシローの社員が務める「スシロー先生」というふたりの先生が登壇し、子ども達に食と海について考えてもらう取組みです。“熱源”とは、ふるさとの海を知り尽くし、豊かで美しい海を未来へ繋げる“熱い”想いをもち、社会を変えるムーブメントの“源”となる人材のことで、全国で約60名の熱源が活動しています。
この日の1限目は、熱源先生として、ウミガメの保護活動などを行っているNPO法人サンクチュアリエヌピーオーの理事長・馬塚丈司さんが講義。ウミガメの生態だけでなく、「ウミガメの保護活動で学んだことは、海岸や海の中がプラスチックで汚れているということ。山、川、平野にあるもの全てが海に行く。なぜなら海が最も低いところにあるから。海はごみ箱みたいになっている。だからビーチクリーンアップを始めた」と子ども達に伝えたように、海洋ごみ問題についても講義しました。海洋ごみ問題では、水槽を使い、海岸の砂からマイクロプラスチックを取り出す方法を実施。馬塚さんは「大人はマイクロプラスチックは小さすぎて拾えないと思っている。だから最初から拾おうと思っていない。しかし、子ども達には拾えるものだと知ってもらいたい」と実験の意図を話しています。
2限目はスシロー先生として志摩亮太さんが講義。スシローの成り立ちや現在の店舗数、人気ネタであるマグロやハマチについて教えました。さらに、「地球環境や海洋ごみなど色々な問題から天然の魚が獲れなくなってしまうかもしれない。そこで、美味しい魚やお寿司を食べ続けてもらうために養殖にもスシローは力を入れている」と、スシローで取り組んでいるハマチの養殖からお寿司になるまでの過程も講義。その後、ハマチの握り寿司を子ども達に食べてもらいました。参加した子ども達は「ハマチが養殖でどのように育っているかなどが知れて、とても楽しくて面白かった」、「今年海に行ったらゴミを拾いたい」と授業の感想を語っています。そして、ふたりの先生は子ども達に、授業をいかして欲しいと考えていて、馬塚さんは「自分たちが大人になった時、どんな社会が良いかというのを認識してもらえたら」と話しています。志摩さんは「海を守らないと将来お寿司を食べられなくなるかもしれない。海を守れるように学んだことをしっかりいかして欲しい」と語っています。