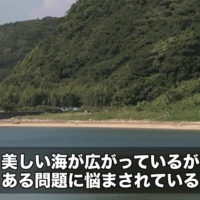香川大学教育学部付属高松小学校では、1年生から6年生までのグループをひとつのクラスにして活動する「縦割り創造活動」が行われています。2020年度の活動のテーマのひとつとして取り上げたのが、「海洋ごみ」です。山田旅生教諭は「今回のプロジェクトは子ども達の発言から始まった。子ども達が社会に役立つものとして、海のごみの問題を取り上げてきた」と言います。2019年7月14日に庵治町で実施された「第26回水ぎわクリーン作戦」に参加した児童が、海洋ごみ問題に関心を持ち、学習テーマとして選んだそうです。
活動では、豊かな海を目指し活動を行っている「里海コンシェルジュ」を学校に招き、海洋ごみの現状を学習。さらに、日本財団と環境省が共同で定めた「秋の海ごみゼロウィーク」の期間中、鎌野海水浴場での清掃にも参加しました。浜辺の清掃を行った児童は「色んなゴミが落ちていて、魚たちが可哀想だと思った」、「ポイ捨てをせずに、しっかり分別してゴミを捨てていきたいと思った」と語っているように、体験からの学びが多かったようです。そして、約1カ月・16回の活動を経て、発表会を実施。それぞれのグループは、ペットボトルが最も多かったという「海ごみランキング」や「海ごみは陸から来たごみが約8割」など、体験したり調べたりしたことを発表しました。その後も、グループ毎に話し合うなど、海洋ごみ問題への意識を高めていきました。山田教諭は「子ども達が主体となって、ごみの問題について親身に関わっていた。色んな方法で発表する子どもの姿を見て、たくさんの人に自分たちの想いや考えが発信できるようになってくれたらと思う」と活動の意義を話しています。また、児童は「自分から積極的に地域のゴミを拾うようにしたい」と、活動を経て意識が変わったと語っています。
素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトinかがわ」
協力:西日本放送株式会社