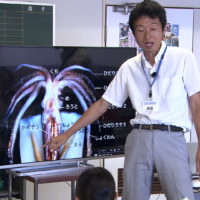熊本県の芦北高校の生徒たちは、芦北湾での「アマモ場づくり」を2002年から行っています。海草「アマモ」が群生するアマモ場は、海の生き物たちの生息場所となる重要な存在です。かつての芦北湾には広大なアマモ場があり、環境省の自然環境保全基礎調査によると、1978年には13haあったそうです。しかし、山からの土砂の流入や海辺の開発など複合的な要因が重なり、1989年前後にほぼ消失したと言われ、現在もヘドロが残る海域があります。
そこで、生徒たちはアマモ場を再生させるため、林業技術を応用した「ロープ式下種更新法」という独自の方法で、活動を始めた当初の30倍にもなる7.5haにまで拡大させてきました。そして、その成果である「ヘドロ海域でのアマモの育成」について、海・水産分野・水環境に関わる研究を行う中高生を応援する「マリンチャレンジプログラム2019九州・沖縄大会」で発表。結果、優秀賞を受賞しました。その後も、専門家からのアドバイスを参考に研究活動を進めていたところ、2020年1月、アマモを5本以上の束にして移植すると生存率が上がることを発見し、さらなる実験を重ねていたところでした。
しかし、7月の豪雨災害で土砂が海に流入。その結果、アマモ場が壊滅的な状態になってしまいました。11月、豪雨後のアマモ場を生徒たちが初めて訪れみると、「ひざ上ぐらいまでヘドロのぬかるみがきたので、とてもビックリした」と語るほど、広範囲にヘドロ化した土砂が堆積。芦北高校・林業科の前島教諭は「微かな期待でアマモの生存確認ができないかと思って行ったが、全く生存確認できなかった。大変ショックだった」と語っています。
しかし、生徒たちは今、マリンチャレンジプログラムでの研究を応用し、新たな取り組みに挑戦しています。ヘドロでの苗づくりを行うなど、先輩から受け継いだ研究をさらに進化させているのです。芦北高校・アマモ班リーダーの橋本魁翔さんは「発見したアマモを5本以上の束にして移植する群集効果などを活用し、『海のゆりかご』とも言われるアマモ場を復活させて、豊かな海にしていきたいと思っている」と意欲を燃やしています。
素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトinくまもと」
協力:熊本朝日放送株式会社