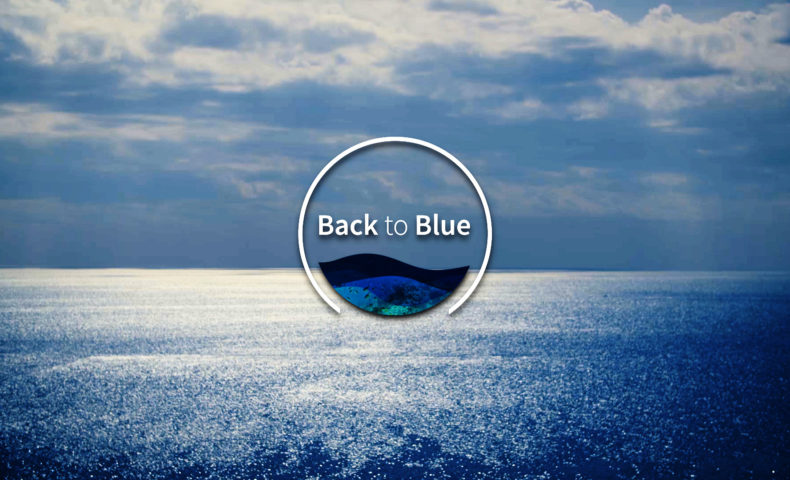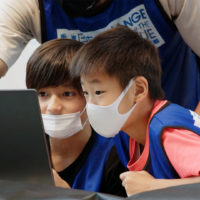今、海洋問題が深刻化し、地球規模で待ったなしの状態となっている。そこで、この問題に取り組むためにイギリスのメディア企業・The Economist Groupと日本財団が創設したのが「Back to Blue」。
日本財団は、7年目を迎え、全国で5000以上のイベントを行ってきた海と日本プロジェクトなどを通じて、海の問題解決をオールジャパンで推進してきた実績がある。しかし、課題も抱えていたという。日本財団の海野光行常務理事は「海洋問題において、私達は全世界にネットワークがあり、科学者がいて、色んな事業をやってきているが、海外に対しての発信ツールがない」と話している。一方で、The Economist Group は、世界中に読者を持つ経済紙「The Economist」を発行する企業。また、毎年 海洋に関する国際会議「ワールドオーシャンサミット」を開催するなど、海の課題にも長年にわたり取り組んできた。実際に、The Economist Groupの編集主幹・チャールズ・ゴッダード氏は「海洋汚染の問題は、人類共通の課題と考えている」と語っている。そんな中、サミットが協働するキッカケだったそうで、海野常務理事は「The Economist Group は、各国でワールドオーシャンサミットをやってきていて、通常は開催国の政府と共催という形で実施している。日本で行う際に、彼らが官邸に相談したところ、共催なら日本財団しかいないと言われたそう。お互い旧知の仲なので話を進めていった」と振り返っている。ただ、サミットはコロナ禍で中止に。しかし、海洋問題解決への想いを持っていた両者は2021年に「Back to Blue」を創設した。
Back to Blueは、エビデンスの活用を重視し、さまざまな活動を行っていて、チャールズ氏は「最近『目に見えない化学物質汚染の波』というリポートを出したが、そうした調査や発信をさまざまな形で行い、化学物質やプラスチック業界がこの問題にどう関わるのかを伝えている」と話す。さらに、「プラスチック管理指数(PMI)」も作成。世界25カ国を対象にプラスチック管理体制や廃プラスチックの流出対策などを評価し、ランク付けしている。ちなみに、日本は高得点を獲得し、2位となっている。チャールズ氏は、プラスチック管理指数について「国連が2024年末までにプラスチック条約を制定するとして、その交渉が始まっている。それは地球環境と海洋における抜本的な削減を目指すものになるはず。私達が公表するプラスチック管理指数が、この歴史的な挑戦に役立てることを願っている」と期待を述べている。
そして、Back to Blueが今、もうひとつ力を入れていることがある。それが、「海の酸性化」。海野常務理事は「3年ぐらい前から漁師の方が『なんか牡蠣がおかしい。軽い』と話していた」と取り組み始めた頃を振り返っている。一体、海の酸性化とは。
素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトin東京」「海と日本プロジェクトin岡山」
協力:株式会社テレビ東京ダイレクト 山陽放送株式会社