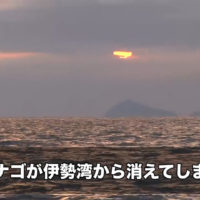京都市内にあるスーパーマーケットの鮮魚コーナー。
こちらに見たことのないマークが。実は、これMSC「海のエコラベル」と呼ばれるもの。イギリス・ロンドンに本部を置く国際非営利団体のMSCが管理している認証制度。そんな「海のエコラベル」は、漁業関係者と消費者が一体となって水産資源を保護していくためのもの。販売されている多くの水産物は、数が減っていて、ギリギリの状態で獲られた水産物なのか、それとも、枯渇しないよう漁業関係者によってしっかり管理されて獲られたものなのか見分けがつかない。そこで、MSC「海のエコラベル」をつけることで、消費者に、この水産物は資源と環境に優しい漁業で獲られたものだと示す。それを消費者が知って購入することで、漁業関係者と消費者が一体となって、水産資源を管理・保護していく取り組みなのだ。
そんなMSC認証について、京都府は全国に先駆けて取り組んできた。その結果、京都府のズワイガニとアカガレイ底引き網漁業は、厳しい審査を経て、2008年にアジアで初めてMSC認証を取得した。MSC「海のエコラベル」について、スーパーで消費者に聞いてみると、「気づいています」や「このラベルがあることによって安心できます」との声が。認証を受けてから約10年、少しずつこのラベルは認知されてきている。また、日本での認知を広げるために大学とスーパーが連携した取り組みも行っている。京都女子大学では、MSC認証について学ぶ講義を開催。実際にMSC認証を受けた水産物が、どのように売られているかも見学している。
京都府漁業協同組合 組織部の濱中貴志次長は、MSC認証の意義について、「漁業者の皆さんが(海の資源を守るために)やっていることは、一般の消費者の皆さんには見えない取り組み。店舗で一般の消費者の皆さんが、マークのついているものを選んで頂く、というのが、漁業関係者の取り組みを支援して頂く、勇気づけて頂くということに繋がっていくと思います」と話す。
素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトin京都」
協力:株式会社京都放送