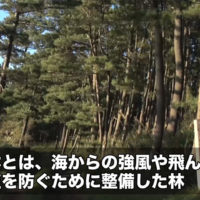●神奈川の海苔名産地で始まった“江戸前 海ぶどう”の陸上養殖
神奈川県横須賀市の走水で、海苔の生産から加工・販売まで一貫して行う「丸良(まるりょう)水産」。走水産の海苔は神奈川県の名産品としても知られていますが、いま丸良水産が挑戦しているのは、沖縄県の特産品「海ぶどう」の陸上養殖です。
●海水温の上昇が走水の海苔にもたらす影響──収穫期の激減・食害
「地球の温暖化で海水温の下がりが悪い。食害や黒潮の蛇行といったいろんな要素があって、海苔を生産する時間が短くなっている」と語るのは、この道46年のベテラン漁師・丸良水産の長塚良治さんです。かつては、彼岸入りの9月20日に種付けをしていたそうですが、今は難しいと嘆いています。「昔は彼岸に(海水温が)23度くらいだった。それが今は10月になっても下がらない。そこから1カ月半近く水温が下がらなかったりする」。海水温の上昇で、走水の海苔も大打撃を受けているのです。
●試行錯誤で育てた“江戸前 海ぶどう”──地元飲食店やフェスで拡大
そこで、2021年から始めたのが、海ぶどうの陸上養殖です。きっかけは、娘夫婦からの提案でした。娘婿の長塚光さんは「海苔のほかに、わかめと昆布の養殖もやっていたが、海水温の上昇から、ここ走水より暑いところのものの方が、(養殖の)将来性があるんじゃないかと考えた」と話しています。しかし、海藻養殖の経験があるとはいえ、海ぶどうの陸上養殖は一筋縄ではいきません。試行錯誤の連続だったといいます。良治さんは「(東京湾は)栄養塩が豊富なゆえに、海藻の中でも貝や魚が嫌いな珪藻が東京湾にはすごくある。沖縄ではほとんど見られないので、それがたかってしまうとなかなか育たない」と養殖の難しさを語っています。そこで、丸良水産では、くみ上げた海水をろ過したり、直射日光を遮るなどの工夫を行いました。その結果、少しずつ生産も安定。茎ごと食べられる海ぶどうは「シャキシャキとした食感でおいしい」と胸を張ります。現在では店頭販売のほか、地元の飲食店が取り入れています。さらに、2022年からは地元の飲食店などと連携し、丸良水産の「江戸前 海ぶどう」を使った限定メニューを展開する「SEA MUSCAT FESTIVAL」を開催。フェスティバルには、イタリアンの巨匠・日髙良実シェフが手掛ける「横須賀アクアマーレ」といった有名店も参加するなど、評判は着実に広がっています。
●「自然にやさしい養殖」と「陸上養殖の拡大」──丸良水産が描く未来の漁業像
海ぶどうの陸上養殖を提案した光さんは、今後は本業の海苔生産でも陸上養殖の可能性を追求していきたいといいます。「今まで陸上では難しかった養殖も、陸上でできれば(漁業を)やれる人も増えたり、かけられる時間が長くなったりすると思う。陸上養殖の拡大をやっていきたい」
そんな光さんを、良治さんは海を糧とする先輩漁師として、より大きな視点で見守っています。「(自然発電の)太陽光パネルをつけるなど、なるべく自然にやさしい漁業を目指していきたい。大事な海を守り切れなかったという思いがあるので、地球の環境をなるべく良い状態で次の世代にバトンタッチしていきたい」
小さな粒が連なって、ひと房の海ぶどうが実るように、こうした挑戦のひとつ一つが海の未来を豊かなものに変えていくでしょう。
*ケイ素ではなく、正しくは「珪藻」です。訂正してお詫び申し上げます。