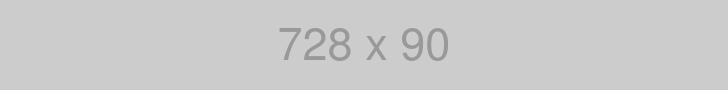都内で「海のそなえシンポジウム~水難事故対策の常識を疑う~」が、2024年6月19日に開催されました。このイベントは、日本財団が企画・統括し、日本ライフセービング協会、日本水難救済会、一般社団法人うみらい環境財団とコンソーシアムを形成して今年度から活動している「海のそなえプロジェクト」が実施しました。このプロジェクトは日本財団「海と日本プロジェクト」の一環です。
「水難事故対策の常識を疑う」をテーマに行われたシンポジウムでは、田村淳さんや藤本美貴さんをはじめ、さまざまな有識者が登壇。まず、田村淳さんと日本財団の常務理事・海野光行さんとでディスカッションが行われ、その中で水難事故の現状が紹介されました。厚生労働省の「交通事故の死者数」と「溺死による死者数」のデータによると、1995年から2022年までの約30年で交通事故の死者数は右肩下がりとなっています。しかし、屋外での溺水事故は減っていません。海野さんは「交通事故は事故検証による要因分析などが行われている。その改善が見られる交通事故と比べると、溺水については科学的証拠に基づいた対策が行われていないのではないかと読み取れる」と語りました。また、今回のシンポジウムに向けて行った水難事故に関する調査結果も発表。1万人以上を対象にして実施したアンケートでは、さまざまな気づきがあったそうで、そのひとつが「溺れの経験は12歳以下が多い」ということだと紹介。溺れの経験がある人に時期を聞いてみると、そのほとんどが小学生以下だったそうです。
「水難事故はなぜ減らないのか」
誰もが抱くこの疑問に正面から向き合うディスカッションが行われました。救難活動の専門家である日本ライフセービング協会の理事で救助救命本部長の石川仁憲さんは溺れを巡る重要なデータを提示。「今回のアンケート調査で17%が溺れた経験があると回答していたが、その約半数が25m以上泳げる能力を持っていましたと回答している」。つまり、プールで泳ぐ力があっても、海や川などの自然水域では溺れてしまうケースもあるということ。泳げることと溺れないことは違うというのです。こうした視点から学校にあける水難教育のアップデートを求める意見も出されました。日本水難救済会の理事長・遠山純司さんは「先生は海のプロではないので、先生自体が(水難事故や対策について)理解していない、情報が入ってこないという状況。その中でどう教えるかというのは限界があると思う。だから、水難事故を減らすためにひとつの進歩をする必要がある」と話しました。そこで、溺水時の対処法として知られている手足を広げて浮く大の字背浮きだけで救助を待つのも、波や流れのあるところでは現実的な方法とはいえないと指摘。イカ泳ぎや立ち泳ぎ、平泳ぎなど、その人が最も得意な泳ぎ方で浮いていればいいと映像も交えながら伝えました。ただ、そもそも溺れた後よりも、「溺れないためのそなえ」の教育が重要だと言います。「(溺れといった)危険な状態に海で陥らないように、どういう“そなえ”をするか。その上で、楽しく海で遊んでもらうというコンセプトで教育内容を組み立てて、それを広く日本全体に広めていく必要があると思う」。
また、中央大学 研究開発機構の機構教授でもある石川さんは、溺れにまつわるもうひとつの興味深いデータを示しました。過去に溺れた経験のある人の方が、片手を大きく左右に振る「助けてサイン」を知っていたり、ライフジャケットの購入・着用率が高かったりしたそう。つまり、“溺れ”という怖い体験を経て、そなえの意識が高まったとのこと。そこで、日本ライフセービング協会は溺れの疑似体験できるVRコンテンツを開発。これによって、そなえの意識を高めてもらうのが狙いです。今後について伺うと「コンテンツはVRの機械さえあれば見れる。色んな地域で活用して欲しい」と話しています。
シンポジウムでは他にも、ライフジャケットに加えて、さまざまな形態の「フローティングアイテム」も登場。ライフジャケットがスタイリッシュになったような「フロートジャケット」、いざという時に膨らますことができる「ブレスレット型膨張式浮力体」といったウェアラブルなものなど、海を楽しみつつ浮力のあるものが紹介されました。株式会社SIGNINGのクリエイティブディレクター・亀山淳史郎さんは「安全であることと楽しかったりとか可愛かったりは分けておく必要がなくて、両方叶えられるものがつくられていくと思うし、そういうものが増えていくといいと思う」と語りました。
「海のそなえプロジェクト」の今後について、海野さんは「今回調査をしてみて、ほとんどの方が12歳以下の時に溺れを経験しているという。これから事業を展開していく上においては、この12歳以下というものをターゲットにして進めていければと思っている」と展望を話しています。