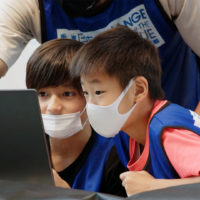11月1日の「灯台記念日」からスタートした「海と灯台ウィーク」。その期間中である11月5日に東京・原宿で開催されたのが、「海と灯台サミット2022」です。日本には3000を超える灯台がありますが、海の道標としてだけでなく、その役割が広がっていて、文化的・歴史的価値が見直されています。サミットは、今後の灯台の存在意義や利活用について語り合い、新たな施策づくりに生かすことが目的で、次世代へ海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として行われました。日本財団の笹川陽平会長は「灯台は、歴史や文化を持ち、日本人にとっての海洋文化資産だが、あまり知られなくなってきている。そこで、サミットを通して理解を深めてもらいたい」と、神奈川県の観音崎灯台から語りかけました。
イベントでは、さまざまな企画が行われ、そのひとつが、「灯台ウィーク イベントリレー中継」です。北海道、石川県、静岡県と中継を繋ぎ、各地の灯台の魅力やウィーク中に開催されているイベントの様子が紹介されました。
また、フランス海洋博物館の灯台専門キュレーターであるヴァンサン・ギグノーさん、直木賞作家の安部龍太郎さん、お城博士の栗原響大さんや海博士の萩原一颯さん、航空写真博士の鈴木陽心さんといった大人顔負けの知識を持つ中高生など、さまざまな有識者が登壇するトークセッションも実施。異業種・異分野の視点も交えながら、灯台の新たな可能性について議論や提案がされ、パネリストとして参加した時事YouTuberのたかまつななさんは「灯台をめぐって新しいプロジェクトがたくさん始まっていると知って、すごくワクワクして楽しい時間だった。今まで灯台は、目的にする場所ではなく、遠くから見るものだと思っていたが、行ってみたいと思った」と振り返っています。そして、日本財団の海野光行常務理事は、「漁に出て夜の灯台を海から見てもらう実証実験」や「灯台サウナを実施予定」など、進めている灯台の利活用に関するモデルづくりを紹介し、「まずは自分たちの近くにある灯台に行ってほしい。そこから灯台がどういうものかを学んでもらって、次はどこの灯台に行こうという形で自分なりに繋げてもらえたら」と語っています。
11月8日までの海と灯台ウィークの期間中は、各地の灯台でイベントが開催されています。この機会に灯台へと足を運んでみてはいかがでしょう。