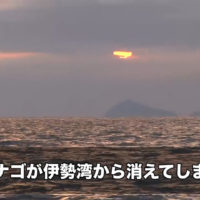富山県氷見市の沖合に広がる海草アマモ。
このような場所は、藻場と呼ばれ、小魚などの生き物を育む「ゆりかご」となっている。
そんな藻場の調査を行っているのは、NPEC環日本海環境協力センターの松村航さん。松村さんは、毎年、氷見沖の藻場について定点調査を行っている。そんな藻場は、全国的に減少傾向。氷見沖でも2016年9月の調査では、「3か月前に調べた時には、アマモが一面生えていたんですけど、それが全く今ない状態です」と松村さんは話す。海に潜って調べてみても、弱弱しく枯れたものや茶色く変色したものばかりだった。
その原因は、海水温の上昇だという。
アマモなどの海草類は、水温の変化に敏感で、30℃を超えると枯れやすいと言われている。実際に、気象庁によると、富山湾の沖合にあたる日本海の中部ブロックではこの100年間で、1.69℃の海面水温の上昇が見られるという。松村さんは、地球温暖化による海水温の上昇が、藻場減少の原因のひとつだと考えている。
しかし、2017年の調査では、「アマモの量は若干去年より多いかなと。それに深いところまでアマモ場があるというような状態です」と松村さんは話すように、藻場がなぜか増えていたのだ。水中カメラを沈め、確認してみると、2016年9月には11カ所しかなかった藻場が、2017年7月には44カ所に増えていることがわかった。詳しく調べてみると、2017年のアマモは、根っこにあたる茎の長さが、わずか5cmと、あまり発達していないことが判明。氷見沖の藻場で増えていたのは、1年で枯れてしまう単年草だったのだ。アマモは水温が上がると、単年草が増える傾向にあるという。
松村さんは「今は温暖化と言われてますし、海水温の上昇もあれば、アマモ場などにも影響してくると思います。ですので、私たち研究者などが、海の中の状況を常に発信していくことが重要だと思っています」と語る。
海のため、そして、私達の未来のために松村さんは調査を続けていく。
素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトin富山県」
協力:富山テレビ放送株式会社